亀山弘能さん(パティシエ)が死去|死因は食道がんだった?
2025年7月、岩手県の名パティシエ・亀山弘能さんが71歳で亡くなったというニュースが飛び込んできました。
「スイーツ界のレジェンド」とも呼ばれた存在の突然の訃報に、驚いた人も多いのではないでしょうか。
ここでは、死因や最期の様子、家族とのエピソードを紹介しながら、その温かい人柄にも触れていきます。
亡くなったのはいつ?死因や闘病生活について
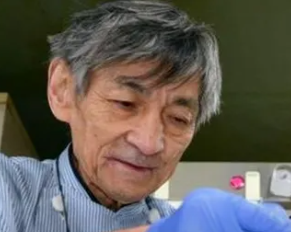
亀山弘能さんが亡くなったのは2025年7月23日。
死因は、30年以上前にいったん寛解していた食道がんの再発でした。
実はこのがん、完治後も定期的に検査を受け続けていたそうです。
再発が判明したのは昨年の秋ごろ。
それでも亀山弘能さんは、今年の春まで店に立ち続けていたとのこと。
仕事への情熱と責任感が並外れていたのは間違いありません。
私もシステムエンジニアとして、プロジェクト納期に追われながら「自分がいなくなったら回らない」と焦ることがありました。
そんなとき、亀山弘能さんのように“人のために働く”という原点を思い出すと、少し肩の力が抜けるんですよね。
最終的には無期限休業の張り紙を出し、入院。
そして、葬儀は近親者のみで行われ、遺骨はご本人の希望で海へと散骨されたそうです。
この潔さもまた、長年スイーツと向き合ってきた職人の哲学なのかもしれません。
最期を見守った家族のコメントが語る想い
長女の櫻子さんは「洋菓子の味も、人を笑顔にしたいという思いも本物でした」と語っています。
この言葉に、亀山弘能さんが大切にしてきた“お菓子の心”がすべて詰まっている気がします。
筆者自身思うのは、“本物”って実は一番むずかしいことだということです。
デザインだけでごまかさない、流行に左右されない、自分の信念を通す──それって職人にもエンジニアにも共通して必要な芯の強さだと思うんです。
櫻子さんのコメントから伝わるのは、単なる親子の絆を超えた「仕事人」としての尊敬でもありました。
店で働く娘として、父の背中をずっと見ていたからこその重みが感じられますね。
このコメント一つで、どれだけ多くの人に“お菓子”以上のものを届けてきたのかが分かります。
続いては、亀山弘能さんが歩んできた波瀾万丈の経歴を見ていきましょう。
華麗な経歴と学歴|元トランペッターから一流パティシエへ
亀山弘能さんのキャリアは、ただの“パティシエ”という枠に収まりません。
大阪でプロのトランペッターとして活動していたところから、製菓の世界に飛び込んだ異色の経歴は、多くの人の関心を集めました。
ここでは、音楽から洋菓子へと転身した背景や、東京での修行、盛岡での開業までをたどります。
大阪での音楽活動と洋菓子の道へ進んだ理由
亀山弘能さんは1954年、岩手県釜石市生まれ。
若い頃は大阪でプロのトランペッターとして活動していました。
しかし、23歳の時に父親から「家業の洋菓子店を継いでほしい」と頼まれ、釜石に戻って菓子づくりを学び始めたそうです。
実は自分も20代の頃、ITとは全く無関係な分野からこの業界に飛び込んだ経験があるので、亀山弘能さんの決断には勝手に親近感を抱いてしまいます。
“好き”や”才能”だけではなく、「誰かの思いに応えるために動く」──その姿勢が人生を大きく変えることもあるんですよね。
その後、5年間の修行を経て上京。
新たな舞台での挑戦が始まります。
東京・三越での経験と「アンナ・マリー」開業まで
上京後、亀山弘能さんは洋菓子研究家・今田美奈子さんの元で技術を学び、東京・日本橋三越のティールームを任されるまでに成長しました。
ここでの経験が、後の独自レシピやスイーツ哲学の原点になったそうです。
そして1988年、盛岡に自身の洋菓子店「アンナ・マリー」を開店。
このお店、見た目はカワイイのに中身は本格派と話題になり、地元に根強いファンを持つ存在になっていきます。
東京での経験と岩手への愛情、その両方が見事に融合した店づくりだったと言えそうです。
亀山弘能さんのプロフィール|人柄が伝わるスイーツ哲学
ここでは、亀山弘能さんの基本的なプロフィールと、どんな“想い”を持ってスイーツに取り組んでいたのかをご紹介します。
言葉の一つひとつから、人としての温かさと、職人としての厳しさが垣間見えるはずです。
出身地や生年月日などの基本情報
・名前:亀山弘能(かめやま ひろのり)
・生年月日:1954年1月1日
・出身地:岩手県釜石市
・職業:パティシエ、ショコラティエ
・開業店舗:アンナ・マリー(盛岡)、洋菓子専科かめやま(釜石)
・指導歴:聖和短期大学フード&製菓学科 講師
・死去:2025年7月23日(享年71歳)
・死因:食道がん再発
お菓子に込めた想いと信念がすごすぎる
亀山弘能さんは、「気持ちを伝えるお菓子を作りたい」という信念を、長年にわたり貫き通してきました。
チョコレートは“作り手の想いを映す鏡”だと語っていたそうです。
素材選びから焼き加減まで、とにかく細部に妥協を許さなかった姿勢は、まさに職人そのもの。
それに、亀山弘能さんは「味は、経験や人間性がにじみ出るもの」とも話していました。
まるで、コードの書き方に人柄が出るように、お菓子作りにも“心”が反映されるんですね。
このスイーツ哲学、今後も多くの人に受け継がれていってほしいと心から思います。
フジコ・ヘミングとの交流|特注ケーキが結んだ深い絆
クラシックファンにはおなじみ、ピアニストのフジコ・ヘミングさんと亀山弘能さんの交流も、多くのメディアで紹介されています。
一見、音楽とお菓子という異なるジャンルに見えますが、その中には確かな“共鳴”がありました。
毎公演前に届く、特別なチョコケーキ
実はフジコ・ヘミングさん、コンサート前になると、必ず「亀山さんのケーキ、お願いできますか?」と連絡を入れていたそうです。
その注文は、決まってチョコレートケーキ。
彼女いわく、「他のケーキだと気分が乗らない」とのこと。
音楽家が舞台に上がる前に、自分を整える“ルーティン”の一つとして、亀山弘能さんのケーキが存在していたわけです。
私も開発本番前は、決まってブラックコーヒーとチョコを口にしますが、人には“集中スイッチ”って必要ですよね。
スイーツで繋がる、芸術家たちの世界
フジコ・ヘミングさん以外にも、小田和正さんや劇団四季の俳優陣など、文化人・芸術家との交流が多数あったそうです。
お菓子は言葉のいらない“共通言語”というわけですね。
このスイーツの力、あなどれません。
つくづく「技術」は手段でしかなく、そこに“誰かを思う心”が乗っかって初めて、人の記憶に残るんだなあと感じます。
震災と復興支援|スイーツで街と心を立て直した男
2011年の東日本大震災では、釜石の店舗が全壊。
それでも、亀山弘能さんは立ち止まりませんでした。
ここでは、絶望の中でもスイーツで前を向かせた復興支援の取り組みに注目してみましょう。
洋菓子専科かめやま、再建への道のり
震災後、「洋菓子専科かめやま」は完全に流されてしまいました。
それでも彼は、「甘いもので人は元気になれる」と信じ、いち早く再建を目指しました。
ボランティアと一緒に店を建て直し、数ヶ月後には限定スイーツの販売も再開。
ただ“戻す”のではなく、より地元に寄り添った店作りを意識していたそうです。
私自身、2011年当時の混乱をIT支援で目の当たりにしたので、このスピード感と行動力には本当に頭が下がります。
若手育成と“街のシンボル”としての再起
再建後は「街のスイーツアンバサダー」として、イベント出店や講演会も積極的にこなし、若手の育成にも力を注いでいました。
震災で失ったものを“未来”へ変える──まさにお菓子で希望を形にした活動です。
岩手に遺した功績|亀山弘能さんが教えてくれたこと
ここまで読んでいただいた方なら、もうお分かりだと思いますが、亀山弘能さんは「ただのパティシエ」ではありませんでした。
最後に、岩手に残した数々の功績を振り返りながら、彼から学べることをまとめておきます。
16人の弟子と「心で作る菓子」の伝承
「お菓子は感情で作るもの」という教えは、レシピを超えた“哲学”として、今も弟子たちに受け継がれているようです。
職人の技術って、データ化できない“にじみ”の部分があるんですよね。
この“にじみ”を伝えられるって、本当の意味での教育者だと思います。
地域との共創、そして永遠に残るスイーツ
地元イベントや百貨店コラボ、新作ケーキの監修など、岩手を代表する「味の顔」として活躍した亀山弘能さん。
それは単に“美味しい”という評価ではなく、「この人がいるから岩手に行く価値がある」と思わせる存在だったのかもしれません。
技術や商品以上に、地域に希望を与え続けたその姿勢こそ、真のプロフェッショナル。
今後のスイーツ業界にとっても、大きな羅針盤となることでしょう。
